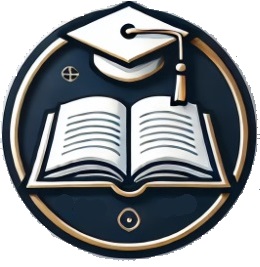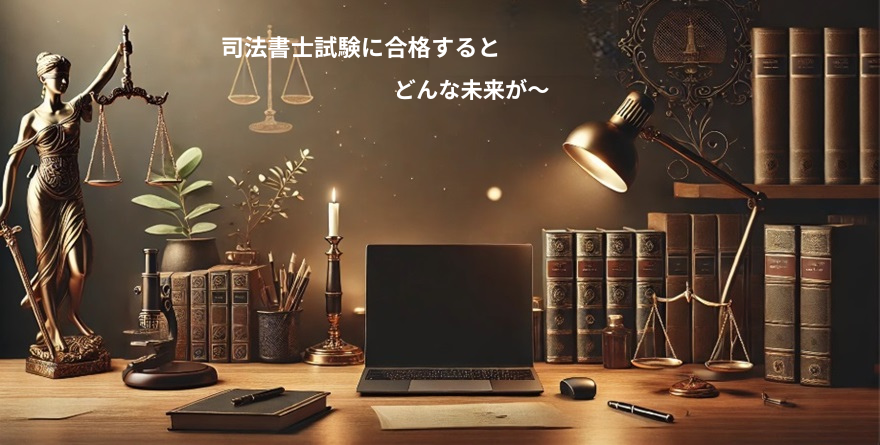司法書士通信講座おすすめ厳選7社を徹底比較!
通信講座を活用して資格取得をめざそう!

Suntip
通信講座を活用して新しい資格を取得しようとする際には、学習ペースやスケジュール管理、モチベーション維持が特に重要です。以下では、1日の過ごし方から1か月・1年の長期的計画、そして心構えまで幅広くお伝えします。参考になれば幸いです。
目次
勉強全体の進め方・学習方法
1. 目標設定と学習計画
- 資格取得の目的を明確にする
「なぜその資格を取りたいのか」を明確にするとモチベーションが保ちやすくなります。転職やスキルアップ、キャリアチェンジなど、自分にとってその資格を取得する意味をしっかり言語化しましょう。 - 合格条件・出題範囲の把握
教材のカリキュラムや試験内容を最初にチェックし、自分の知識レベルと試験内容に差がどれくらいあるかを把握します。合格基準や出題形式(択一式、記述式など)を知り、必要な勉強量を逆算します。 - 教材の確認と学習ペースの見積もり
通信講座のテキスト量や映像講義の長さを把握し、どの程度の時間を割けば1周目が終わるかを計算してみましょう。講義動画の倍速視聴や、テキストを要点ごとにまとめる方法など、効率的に進める工夫も大切です。

2. 学習テクニック
- アウトプット重視の学習
ただ読んだり講義を視聴するだけではなく、問題演習や過去問、模擬問題などを解くアウトプット学習に力を入れましょう。 - スキマ時間の有効活用
音声教材やスマホのアプリなどを使えば、移動時間・待ち時間なども活用できます。 - 復習サイクルの確立
学習した日、1日後、1週間後、1か月後に再度見直すなど、定期的に復習することで長期記憶に定着させます(いわゆる“エビングハウスの忘却曲線”に基づいた復習)。
3. 通信講座ならではの活用方法
- 添削指導や講師への質問制度を活かす
通信講座では、添削指導や質問フォーラムが設けられていることが多いです。分からないことを放置せず、積極的に質問して理解を深めましょう。 - 学習コミュニティを活用する
同じ講座を受講している人同士が情報交換できる場合は、交流から得られる刺激や勉強のコツが大いに参考になります。またモチベーション維持に役立ちます。
1日の時間の使い方
資格試験合格に向けた学習計画や心構えは、人によって使える時間が大きく異なります。そこで「1日24時間フルに使える人(専業で学習できる人)」と「仕事などでスキマ時間しか使えない人(サラリーマンや兼業学習者)」に分けて、それぞれの学習方法・計画の立て方をお伝えします。
A. 1日24時間フルに使える人の場合
① 時間割を細かく設定してメリハリをつける
- 1日の学習時間帯を明確化
1日丸ごと勉強に充てられるとはいえ、ただダラダラと勉強していては集中力が続きません。朝のゴールデンタイム(起床後2~3時間)や夕方など、自分が最も集中しやすい時間帯を特に大切にします。 - ポモドーロ・テクニックや1~2時間単位で区切る
学習時間が長い分、休憩の取り方や時間管理が重要になります。1~2時間学習→15分休憩など、自分なりのサイクルを決めると疲労感が減り、生産性も高まります。
② インプットとアウトプットをバランス良く
- インプット(講義視聴・テキスト読解)
1日当たりの学習時間が長く取れる分、テキストや動画講義を一気に進めすぎないよう注意します。時間があるからこそ「理解不足なのに進んでしまう」リスクもあるため、理解度を随時確認しましょう。 - アウトプット(問題演習・過去問)
問題演習の際には、1日に大量の問題を解きすぎず、復習時間をしっかり確保することが大切です。誤答した問題の原因分析や解説の確認を丁寧に行い、次に間違えないように対策します。
③ 長期的な視点でのスケジュール管理
- “詰め込み”を避ける
1日あたりに確保できる時間が多いからといって、最初のうちから12時間、14時間と無理に詰め込むと burnout (燃え尽き) に陥りやすくなります。長期的に学習を継続できるペース配分を考えましょう。 - 週単位・月単位で進捗を振り返る
例えば、毎週末に「今週学んだ範囲」「理解が不十分なところ」を整理し、必要があれば翌週に補習時間を加えるなどリスケジュールします。学習進捗を可視化するツール(エクセルやタスク管理アプリなど)も活用しやすいです。
④ 体調管理とリフレッシュ
- 適度な運動と十分な睡眠
時間があるからこそ、身体を動かす時間やしっかりした睡眠を確保して、勉強の効率を高めましょう。 - 集中力を維持するためのオン・オフ
平日の昼間にカフェや図書館など場所を変えて勉強する方法も有効です。一ヶ所にこもりすぎるより、環境を変えることで気分転換になり、学習効果が高まる場合もあります。
B.仕事をしながら、スキマ時間を利用して勉強する人の場合
① 限られた時間を最大限活用する
- 朝の時間を活用
出社前の1時間、あるいは30分でも確保できるなら、有効に使います。朝の方が頭がスッキリしているため、新しい知識を吸収するインプット作業や暗記系に向いています。
- 通勤時間や休憩時間のスキマ学習
スマートフォンやタブレットを使い、過去問や一問一答アプリ、音声教材などを活用します。「5分単位」での学習でも積み重ねれば大きな差になります。
② 1日のタイムスケジュール例(サラリーマン想定)
- 朝(起床~出社まで)
30分~1時間の勉強時間を確保(テキスト読み、暗記、問題演習の軽いアウトプット) - 昼休憩
15~30分のスキマ学習(スマホアプリで過去問を解く・テキストの要点チェック) - 仕事終了後~就寝前
帰宅後に30分~1時間の学習(その日の復習・翌日の予習)
夜は疲れがたまっていることが多いため、無理な詰め込みよりも、復習や理解度チェック、軽めの暗記確認などに使うのがおすすめです。
③ 勉強計画の立て方と優先順位
- 重要分野・頻出分野を最優先
限られた時間の中では、闇雲に全範囲を完璧にしようとしないことが大事です。試験の頻出範囲や配点の高い分野、苦手意識のある分野を優先的に学習します。 - 学習計画は週ごと、月ごとに無理のない設定を
「1週間でテキスト1章+過去問10問」など、達成可能な範囲の目標を立てます。達成感を得ることでモチベーションを維持しやすくなります。
④ モチベーション維持と効率化の工夫
- 学習コミュニティやSNSの活用
一緒に勉強している人の存在が励みになる場合もあります。通信講座のフォーラムやSNS(Twitterや学習管理アプリ)で勉強記録を共有するなど、仲間がいる環境を作ると継続しやすくなります。 - タスク分割の徹底
“テキストを1章読む”というのはざっくりしすぎです。たとえば「各節ごとに細かく分割してチェックリストを作る」「覚えるべきキーワードを箇条書きにして何個覚えたかカウントする」など、どこまでやったかが分かる仕組みを作ると達成感が得やすくなります。 - 疲れやストレスのケア
仕事との両立では疲労が大きく、モチベーション低下に繋がることもあります。週1回は勉強をオフにする日を作るなど、休むタイミングを意識すると逆に勉強効率が上がります。
C.まとめ
- 1日24時間使える人は、時間がある分こそメリハリと休息のバランスを取り、集中力を長期間維持する工夫が必要です。詰め込み過ぎによる燃え尽きに注意しつつ、インプットだけでなく問題演習や理解度チェックをしっかり行いましょう。
- 仕事や家事・育児と両立している人は、隙間時間を活用しながら、試験日から逆算して無理のない計画を立てることが大切です。限られた時間であっても、頻出範囲や苦手分野に集中し、タスクを小分けにして確実にこなすことで、着実な力がついてきます。
どちらの立場でも、合格へのモチベーション(資格取得の目的)を明確にすることが継続のカギです。自分の学習スタイルや環境に合わせて計画を立て、コツコツと学習を積み上げていきましょう。応援しています。
1か月間の勉強計画
1. 月初に立てる目標
- 学習進捗目標を数値化する
「テキスト第○章まで終了」「問題演習を○回やる」など、具体的に数値化します。 - 期限(締切)を決める
通信講座には添削課題などの締切があることもあります。締切を意識しつつ、余裕をもって進められる計画を立てましょう。
2. スケジュールの具体化
- 週ごとの目標に落とし込む
1か月後の目標を達成するために、週単位で小目標を設定します。そうすることで計画が立てやすくなり、進捗を管理しやすくなります。 - 学習量のバランスを意識
インプット(講義動画やテキスト)だけでなく、アウトプット(問題演習、過去問)に使う時間も確保します。
3. 進捗管理と調整
- 振り返り&リスケジュール
毎週末や毎月末などに学習の進捗を振り返り、予定より遅れている場合は翌週や翌月に補填する計画を立てます。 - モチベーション管理
学習を計画通りに実行できたら、自分に小さなご褒美を与える、SNSで勉強記録を公開するなど、続けたくなる工夫をします。
1年間の長期計画
1. 合格までのロードマップ作成
- 試験日をゴールとして逆算する
試験日や申し込み時期などを基準にして、何か月前にどのレベルまで到達しておく必要があるか逆算します。 - 学習のフェーズ分け
1年の中でインプット中心の期間、問題演習中心の期間、模擬試験や総復習の期間など、段階を分けるとメリハリがつきます。
2. 定期的な模試・過去問演習
- 模試や過去問は早めに取り組む
試験形式に慣れるためにも、最低でも数か月前から過去問を繰り返し解くことが大切です。苦手分野を早期に発見でき、学習計画の修正に活かせます。 - 年度ごとの出題傾向を分析
資格試験によっては、年度ごとに出題の傾向が変わることもあります。過去数年分を分析して、頻出分野に力を入れましょう。
3. 長期的モチベーション維持のコツ
- モチベーションの源を定期的に確認
資格取得の目的や将来のビジョンを定期的に思い出すと、長期戦でもやる気を失いにくくなります。 - 短期目標の達成で成功体験を積む
長期目標だけを見ていると途中で挫折しやすくなります。1か月ごと、3か月ごとに達成できるような短期目標を設け、達成感を味わうようにしましょう。
資格試験に臨むための心構え
- 自己効力感を高める
「自分ならできる」という感覚がないと、困難にぶつかったときに諦めやすくなります。小さな成功を積み重ねて、少しずつ自分の力を信じられるようにしましょう。 - 失敗を恐れずチャレンジする
最初から完璧な学習を求める必要はありません。分からない箇所が出るのは当たり前、最初は問題演習で間違えるのが普通、と気楽に考えましょう。間違いを通して成長できます。 - 継続のコツを知る
どんな優れた計画でも、続かなければ成果は得られません。続けやすい仕組み(学習記録ツールの活用、SNSでの進捗報告、仲間との声掛けなど)を取り入れましょう。 - 生活全般を整える
勉強だけに集中して睡眠や食事を疎かにすると、体調を崩してしまったり、集中力が落ちたりします。仕事・家事・勉強のバランスを整え、健康管理を大切にしましょう。 - 試験直前はペースを崩さない
試験直前期に新しいことを詰め込もうとしすぎると混乱しがちです。総復習を中心に、過去問演習や苦手分野の確認をしっかり行い、試験当日は十分な睡眠と適度な休息をとりましょう。
「強い意志」と「継続の力」
通信講座を利用して資格取得を目指す場合、柔軟な学習スタイルを活かしつつ、いかに計画的に進められるかが鍵です。
- 1日の時間管理をしっかり行い、朝の時間やスキマ時間を有効に使う。
- 1か月の学習計画では、週ごとに小目標を設定し、振り返り・調整を繰り返す。
- 1年という長期スパンでは、試験日から逆算して学習フェーズを分け、過去問や模試を活用して実践力を高める。
- 心構えとしては、モチベーションを維持できる仕組みを作り、失敗を恐れずに継続し、生活習慣と体調管理をしっかり行う。
これらを踏まえて、日々の勉強を着実に積み上げていけば、合格に近づくはずです。自分に合った勉強ペースと学習スタイルを見つけ、無理なくコツコツと進めてください。
資格取得までの道のりは長いかもしれませんが、必ず資格取得するという「強い意志」と諦めずに続けるという「継続の力」こそ、合格への最短距離です。この2つがあれば必ず合格できるでしょう~応援しています。